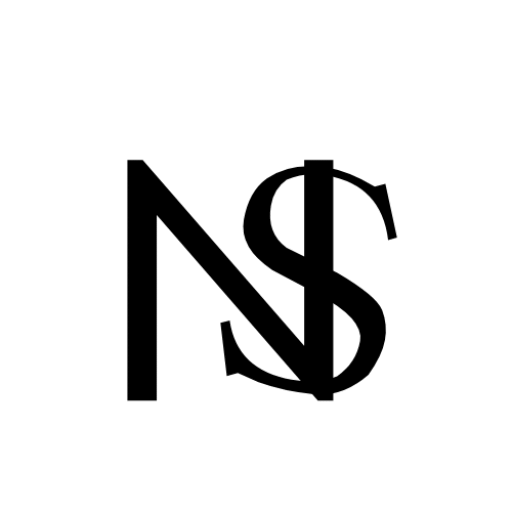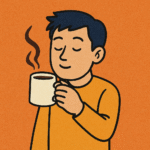寝過ぎた時どうすればいい?完全ガイド

昼夜交代勤務をしていると
ある悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。
それはついつい寝過ぎてしまうこと。
私自身も何回も、
いや何十回も経験があります。
そしてその度に後悔と体調不良に悩まされます。
ではそんな時どのようにすればいいのか。
今回は寝過ぎてしまった時に役立つ知識を
たっぷりと詰め込んだ記事となっております。
ついつい寝過ぎてしまう人、
必見ですよ!
寝過ぎてしまうとなぜ体調が悪くなるのか
生命活動に欠かせない睡眠。
その睡眠も短いと体に悪影響をもたらしますが、
適切な時間を超えて長過ぎても体に悪影響をもたらします。
誰しもが経験があるのではないでしょうか。
それはなぜなのか。
一つ一つ解説をしていきます。
脳の血管拡張と神経刺激
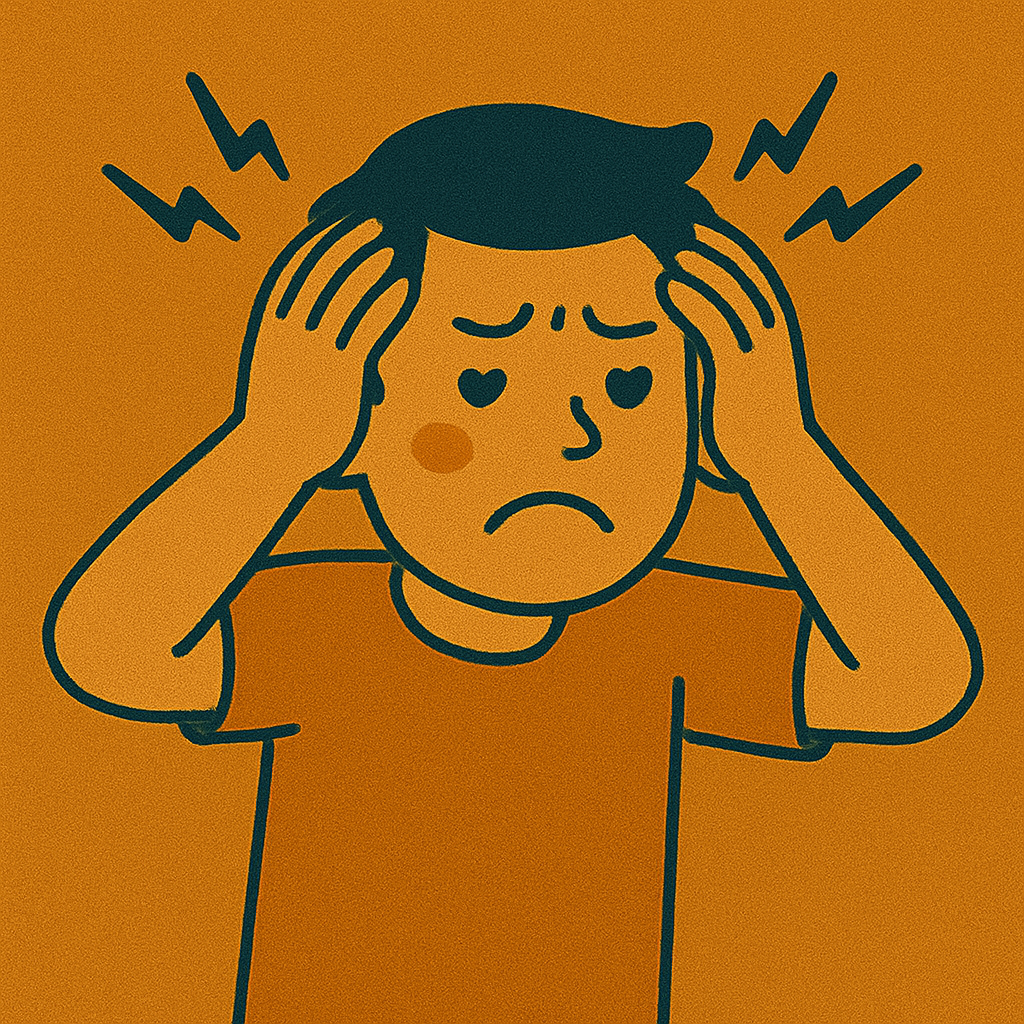
長時間眠ることで脳の血管が拡張し、周辺の神経を刺激します。
これにより頭痛や吐き気といった症状が発生しやすくなります。
特に「片頭痛」は脳の血管拡張によるもので、
ズキズキとした痛みや吐き気を伴うことが多いです。
また起床時の急激な血流変化も、
三叉神経への刺激を強め頭痛を引き起こしやすくします。
寝過ぎ=片頭痛と認識している人は多いのではないでしょうか。
私も寝過ぎたと感じる一番の体調不良は片頭痛の現れです。
自律神経のバランスの乱れ

睡眠中は心身を休める副交感神経が優位になります。
寝過ぎてしまうと起床時にも副交感神経が優位なままで、
交感神経への切り替えがうまくいきません。
そのため「眠い」「だるい」「しんどい」といった
強い倦怠感や疲労感が残ります。
長時間寝た方がスッキリするどころか
目覚めが悪いということはよくありますよね。
血流の悪化と筋肉への負担

長時間同じ姿勢で寝ていると、
首や肩、腰などに負担がかかり血流が悪化します。
これにより筋肉に疲労物質がたまり、
起床時にだるさや筋肉痛、腰痛などを感じやすくなります。
寝過ぎて体がバキバキになっている経験ありませんか。
私はよくあります。
サーカディアンリズムの乱れ

寝過ぎると生活リズムが崩れ、
サーカディアンリズムがずれてしまいます。
これにより「社会的時差ぼけ」と呼ばれる状態になり、
眠気やだるさ、夜の寝つきの悪さなどが生じます。
またサーカディアンリズムの乱れは、
ホルモン分泌や体温調節、食欲にも悪影響を与えます。
寝過ぎてしまうとそこからリズムが崩れて、
ずるずると睡眠時間がずれてしまうのはこのためです。
ホルモンバランスの変化と代謝の低下

寝過ぎは食欲を調整するホルモン(レプチンやグレリン)のバランスを崩し、
過食や肥満の原因になることがあります。
それとは逆に寝過ぎによって体のリズムが崩れると、
消化器系の働きが低下し「気持ち悪い」「胃もたれ」「食欲がわかない」
といった症状が出ることがあります。
また当然ですが活動量が減るため
基礎代謝が低下し、体重増加や糖尿病、心臓病のリスクも高まります。
私も寝過ぎた日に限ってついつい食べすぎてしまったりします。
というより無性に体に悪いものが食べたくなるというか・・・
精神面への影響

寝過ぎてしまうと脳内の神経伝達物質(セロトニンやノルアドレナリン)
のバランスが崩れます。
それによって精神的な安定が保てなくなり、
気分の落ち込みや意欲の低下が生じやすくなります。
またうつ症状などが出やすくなることも報告されています。
さらに寝過ぎによる精神的な不調は、
さらに活動意欲や気力を奪い、ますます「寝て過ごす」時間が増えるという悪循環に陥りやすいのが特徴です。
寝過ぎてしまった自分に対してめちゃくちゃ落ち込んで
ブルーな気持ちになってしまうのはこういった仕組みがあるのです。
睡眠時無呼吸症候群、過眠症、うつ病、甲状腺機能低下症など
身体的・精神的な疾患が原因で寝過ぎる場合もあります。
日中の強い眠気や異常な過眠が続く場合は、医療機関への相談が必要です。
また生まれつき長時間の睡眠を必要とする
「ロングスリーパー」と呼ばれる体質の人もいます。
この場合は一般的に寝過ぎとされる時間の睡眠が
そもそも必要だったりします。
寝過ぎてしまった場合の対処は
では次に寝過ぎてしまった時にどのように対処すればいいのかを
徹底的に解説していきます。
太陽または強い光を浴びる

光にはサーカディアンリズムをリセットする強い効果があります。
光を浴びることで、脳内の「メラトニン」分泌が止まり、
覚醒ホルモンである「セロトニン」が活性化します。
これにより眠気が取れ、活動がしやすくなります。
人工照明より太陽光の方が
サーカディアンリズムへの影響が大きいですが、
夜勤などでどうしても浴びれない人は人口照明でも効果はあります。
軽い運動・ストレッチで血流を促進

長時間寝ていると筋肉が硬直し血流が悪くなります。
軽い運動で血流を促し筋肉の緊張やだるさ腰痛を和らげましょう。
⚫︎おすすめの運動
・ウォーキング(10分程度)
外に出てゆっくり歩くだけでもOKです。
筋肉にたまった乳酸が流れ、血流がアップします。
呼吸も深くなり脳に新鮮な酸素が送られるため頭がスッキリしやすくなります。
・その場で足踏みや軽い体操
雨の日や外出が難しい場合は、室内でその場足踏みやラジオ体操なども有効です。
全身を大きく動かす必要はなく、リズミカルに体を動かすことがポイントです。
⚫︎おすすめのストレッチ
・全身の背伸びストレッチ
仰向けになり両手を頭の上に伸ばします。
次に両足のつま先を下に伸ばして全身で「大」の字になります。
この状態で5秒間しっかり伸ばしたら力を抜くを3回繰り返します。
無理せず心地よい範囲で伸ばしましょう。
・手首、足首回しストレッチ
仰向けで手足の指を握ったり開いたりを5回繰り返します。
その後、手首と足首をゆっくりと5回ずつ回します。
・キャット&ドック
四つん這いで背中を丸め(猫のポーズ)、
次に背中を反らせる(犬のポーズ)をゆっくりと交互に行います。
やると結構気持ちがいいです。
朝食を食べる
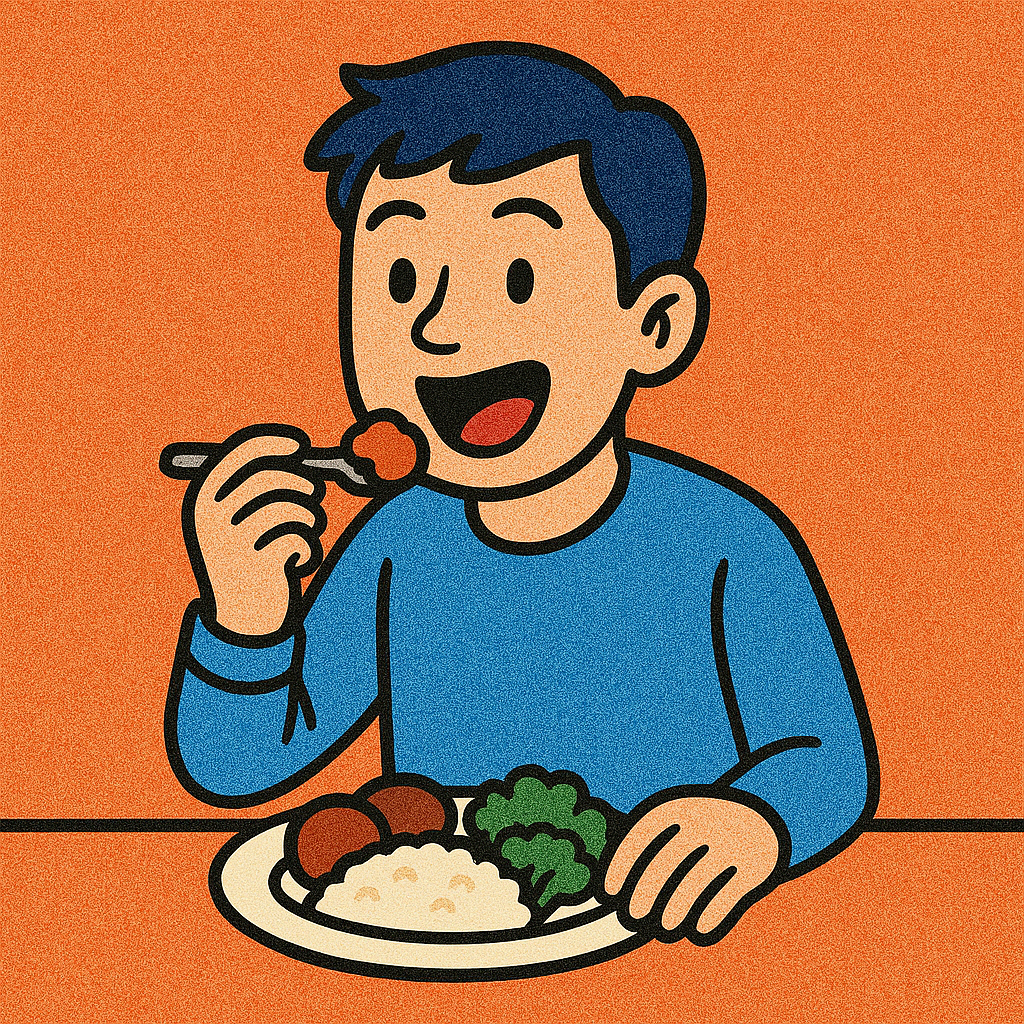
朝食をとることで胃腸や肝臓などの臓器のリズムが整い、
全身の活動モードへの切り替えがスムーズになります。
また朝食を摂ると血糖値が上昇し、
インスリンが分泌されます。
これがサーカディアンリズムの調節や
自律神経のバランス回復に役立ちます。
タイミングとしては起床後1時間以内が望ましいとされています。
できるだけ早く朝食を食べることで
サーカディアンリズムのずれを最小限に抑えられます。
入浴する

入浴による温熱効果で末梢神経が拡張し、
全身の血行が促進されます。
これにより体内の疲労物質や老廃物の排出がスムーズになり、
疲労回復効果が得られます。
湯船に浸かることでシャワーよりも全身の血流が良くなり、
だるさや重さが取れやすくなります。
またぬるめのお湯に浸かることで副交感神経が優位になり、
心身ともにリラックスできます。
寝過ぎで乱れた自律神経のバランスを整え、
ストレスや緊張を和らげる効果も期待できます。
アロマオイルや入浴剤を使うと、さらにリラックス効果が高まります。
頭痛がする場合

寝過ぎによる頭痛には「片頭痛」と「緊張型頭痛」の2つのタイプがあり、それぞれ対処法が異なります。
⚫︎片頭痛の場合
・冷やす
痛む部分や首の後ろ(特に「盆の窪」と呼ばれるくぼみ)を
保冷剤や冷却シートで冷やすと、拡張した血管が収縮し痛みが和らぎます。
・暗く静かな場所で安静にする
光や音の刺激を避け、静かな部屋で横になりましょう。
・カフェインを適量摂取
コーヒーや紅茶などカフェインを含む飲み物は血管収縮作用があり、
痛みの軽減に役立つ場合があります。
ただし、飲み過ぎには注意してください。
・温めるのは避ける
入浴や蒸しタオルで温めると悪化することがあるため、
片頭痛の場合は冷やすことを優先します。
⚫︎緊張型頭痛の場合
・温める
目や肩、首周辺を蒸しタオルやお風呂で温めると、
筋肉の緊張がほぐれ血流が改善します。
・軽い運動やストレッチ
肩や首、背中を軽く動かすことで血行を促進し、
痛みの緩和につながります。
・マッサージ
首や肩を優しくマッサージするのも効果的です。
ただし、「片頭痛」「緊張型頭痛」に関係なく
頭痛が長引く、頻繁に繰り返す、吐き気や嘔吐、
手足のしびれなど他の症状を伴う場合は、
他の疾患の可能性もあるため早めに医療機関を受診しましょう。
寝過ぎることを防ぐには
では寝過ぎてしまうことを防ぐにはどうすればいいか。
それには個人ごとに違う寝過ぎてしまう原因を
特定するがとても大切です。
しかし私が思うにほとんどがこの2つの
どちらかだと思われます。
・日々の睡眠時間がバラバラになっている
・睡眠の質が悪い
日々の睡眠時間を固定できるのならば、
それに伴ってサーカディアンリズムを構成していけばいいのですが、
どうしても睡眠時間がバラバラになってしまうのが現代人だと思います。
私自身も昼夜交代勤務をしていますので、
睡眠時間はバラバラのぐちゃぐちゃです。
そこで意識して欲しいのは睡眠の質についてです。
なのでここでは寝過ぎを防ぐ、
睡眠の質が向上するポイントを解説していきます。
起きている間の活動を充実させる

たくさんの予定をこなしてヘトヘトになった日は泥のように眠れる。
ほとんどの人が経験あるのではないでしょうか。
そうです。ある程度の疲労は睡眠の質向上に役立ちます。
(過度な疲労は逆効果です。)
ではどのように起きている時間を充実させるのか。
私のおすすめは、
その日のやりたいことを紙などに書き出すことです。
人間やることが定まっていないと
どうしてもダラダラと過ごしてしまう生き物です。
少しだけYoutubeを見ようと思ったら、
少しだけスマホゲームをしようとしたら、
少しだけ漫画を読もうとしたら、
気がついたら1時間経っているなんてよくある話です。
でも仕事に出勤する前にスマホをいじっていても、
しっかり時間になったらやめられるはずです。
やるべきことが明確だからです。
平日は朝から晩まで仕事で忙しいという人が
ほとんどかと思いますので、
ぜひ休日に何をするのか、したいのかを書き出してみてください。
朝起きてから書き出してもいいですし、
平日の間にちょこちょこ書き溜めていってもいいです。
休日が充実して、睡眠の質も上がるのでおすすめです。
就寝前の食事、水分摂取、スマホの終了時間を決める

就寝前の食事の時間や水分摂取、
スマホやPCなどの電子機器の使用も睡眠の質に直結します。
食事を摂ると消化活動が活発になります。
すると体を休めにくくなり睡眠の質を大きく下げてしまいます。
私は就寝時間の3時間前には食事を終えるようにしています。
水分摂取に関しては睡眠中も水分が失われるため、
必ず必要ですが取り過ぎてしまうと夜間に尿意で
起きてしまいます。
それにより睡眠の質を下げてしまいます。
私は就寝2時間前に水分摂取を終えるようにしています。
(睡眠中に尿意で起きることがほとんどなくなりました。)
スマホなどの電子機器も睡眠の質を下げてしまいます。
スマホやパソコン、テレビなどの画面から発せられるブルーライトは、
睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑えます。
これにより脳が「昼間」と錯覚し寝つきが悪くなったり、
睡眠の質を下げてしまいます。
こちらはなかなか難しいですが、
私は就寝1時間前には電子機器を使用しないようにしています。
この時間を使って家族とコミュニケーションを取ったり、
紙の本で読書をしたり、ジャーナルを書いたりしています。
仮眠、カフェインに気をつける
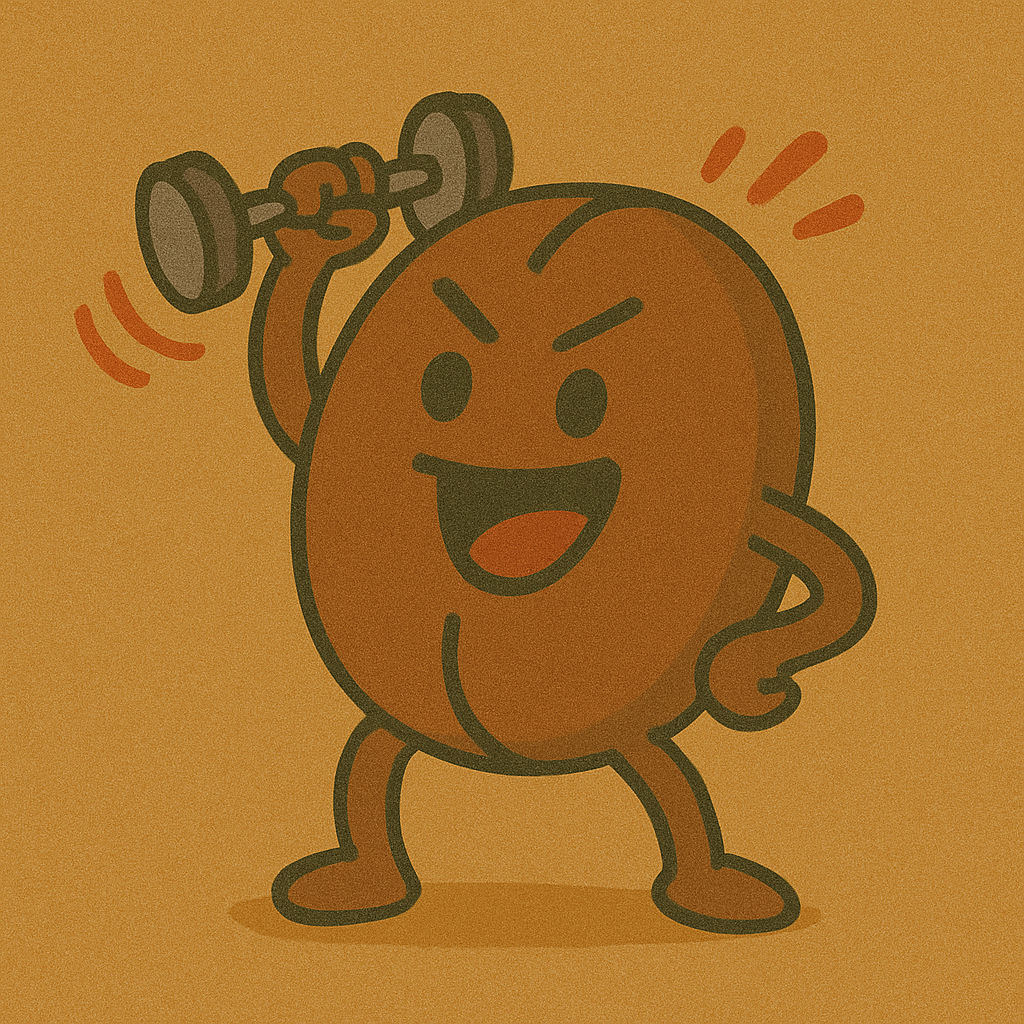
日中についつい寝過ぎてしまって
夜眠れなかった経験は誰しもがあると思います。
(私も数え切れないくらいあります。)
個人差はありますが仮眠は15分〜30分に抑えるのが
理想とされています。
また短い仮眠でも就寝前の仮眠は睡眠の質に影響しますので、
就寝5時間前までに終えましょう。
私も本当に眠たい時だけ昼間に15分〜30分仮眠をとります。
またカフェインも注意が必要です。
覚醒効果もあり仕事の相棒にしている人も多いと思いますが、
実はカフェインはかなりの時間体に残ってしまうのです。
カフェインを完全に体外に排出するには個人差はあれど、
ほぼ24時間以上かかってしまいます。
そのため摂取したカフェインの量が半分になる、
「半減期」を目安にするといいとされています。
そちらも個人差がありますが約6時間ほどとされています。
(半分になるのが約6時間なのに完全に抜けるのが24時間かかるのは
6時間で半分になり12時間でさらに半分になり18時間でさらに半分に・・・
となり完全に抜け切るにには長い時間が必要なのです。)
そのため就寝時間の6時間前にはカフェインの摂取は
控えた方がいいでしょう。
私も昼以降はカフェインを摂取しないようにしています。
カフェインについて詳しく知りたい方は
こちらの記事もおすすめです↓
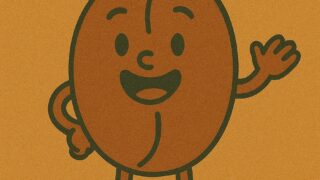
まとめ
寝過ぎてしまう。
誰しもが経験のあることだと思います。
今回は寝過ぎてしまうことによる影響、
寝過ぎてしまった場合の対処方法、
寝過ぎてしまうことの対策を徹底解説してきました。
寝過ぎた時の辛さはよくわかります。
「1日を無駄にした・・・」
「なんで起きれなかったんだろう」
「頭が痛い」
そんな後悔を何度してきたか。
特に昼夜交代勤務をしているとどうしても
寝過ぎてしまう確率も高くなってしまいます。
それでも対処すること、
対策できることはあります。
今回紹介した内容を実践してみてください。
寝過ぎてしまい自暴自棄にならないでください。
大丈夫です。
無理なくできるところから実践してみましょう。
やらない後悔よりやる後悔を。
みなさんの明日がより良いものになることを
心から祈っています。