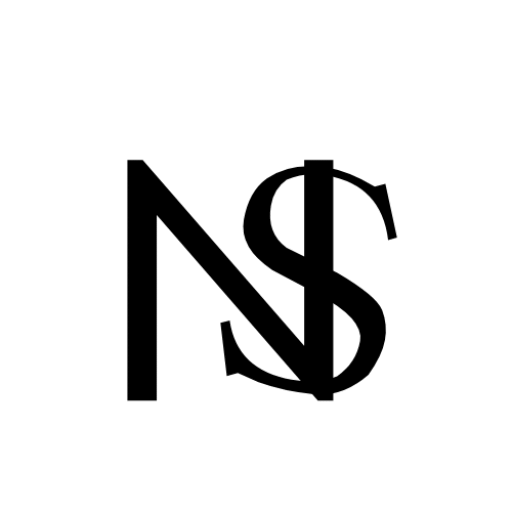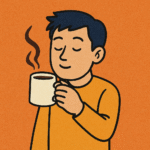明日から使える!音楽が体に与える影響

私たちの生活に深く根付いている「音楽」。
通勤中、休憩中、ドライブ中、家事をする時、リラックスする時などなど
普段から日常の様々な場面で耳にするかと思います。
音楽は単なる娯楽や気分転換と思われがちかもしれませんが、
体に対して多様な影響を及ぼしていると近年の研究で明らかになってきています。
今回は音楽にどのような効果があるのか、
また明日の仕事から実践できる具体的な活用方法を徹底解説します。
音楽と人類の付き合い
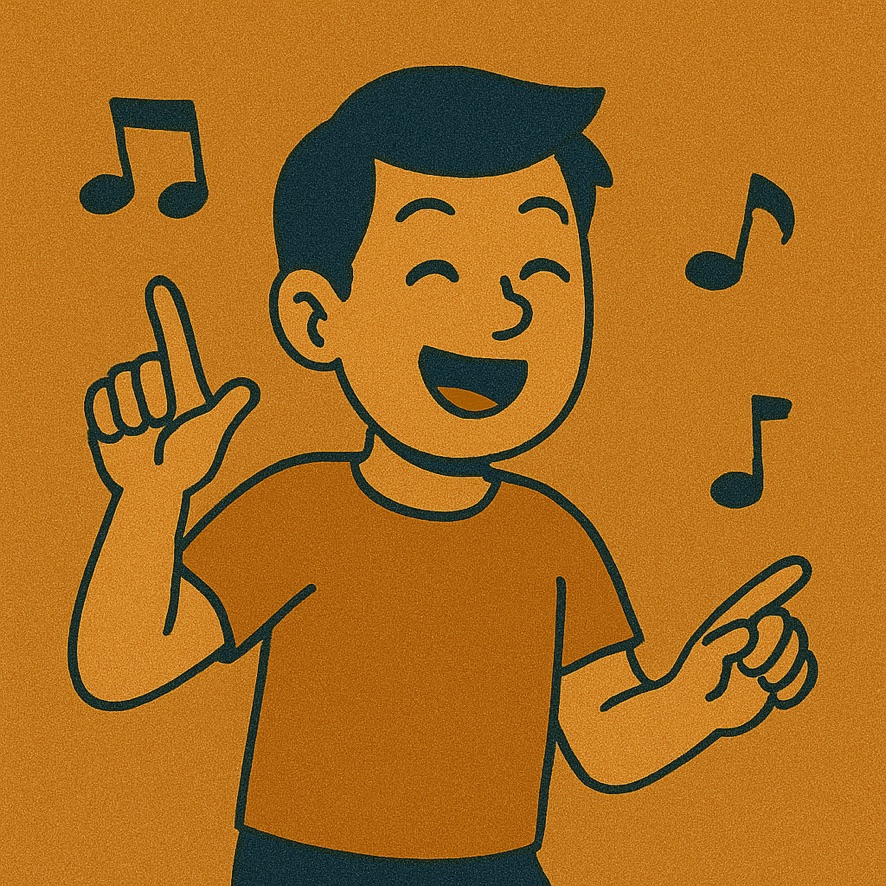
音楽がいつからあるのか?
その起源はいまだに謎に包まれています。
少なくとも紀元前3000年ごろには笛や太鼓などの
楽器が使われ、儀式や祭りで音楽が演奏されていた
記録や遺物が残っています。
つまり最低でも5000年以上の付き合いとなるのです。
本当にすごいですよね。
それほど古くから人類は音楽と付き合ってきたのです。
音楽が体に与える影響
では、そんな音楽が我々の体にどのような影響を与えるのか、
またどんな音楽がいいのかを徹底解説していきます。
リラックス効果とストレスの低減

音楽を聞くことで脳内ではドーパミン、セロトニン、
エンドルフィンといった神経物質が分泌されます。
これらの物質が不安を感じるホルモンの分泌を抑制し
同時にリラックス効果をもたらしてくれます。
またリラックス効果のある音楽は副交感神経を優位にして
自律神経のバランスを整える効果があります。
さらにコルチゾール値が下がりストレスが実際に軽減される
といったデータもあります。
・クラシック音楽(特にモーツァルトやバッハなど)
1/fゆらぎと呼ばれる自然なリズムが含まれ、リラックス効果が高い。
・自然音(川のせせらぎ、鳥のさえずりなど)
自然界のリズムにも心身を落ち着かあえる働きがあります。
・高周波成分を含む音楽(4000Hz以上)
高い周波数が豊富な音楽は大脳を活性化し、
ストレスホルモンが低減します。
・自分の好きな音楽
ジャンルに関係なく、聴いてて心地よいと感じる音楽は効果的です。
免疫力の向上

ストレスが軽減されることにより自律神経が整い、
免疫系の働きが活発になります。
また音楽を聴いた後は唾液中の分泌型lgAが増加することが
最近の研究でわかっています。
このことで口腔内のウイルスや最近の侵入を防ぎやすくなり、
免疫力が向上します。
さらに副交感神経を優位にする音楽は体表面温度の上昇、
血流の改善などが確認されリンパ球や免疫細胞の働きを
高めるとわかっています。
・クラシック音楽(特にモーツァルトやバッハなど)
副交感神経を優位にし免疫細胞の働きを助けます。
・ゆったりしたテンポ(60〜70BPM)の曲
安定時の心拍数に近いテンポの音楽は自律神経を整える効果があります。
・自然音(川のせせらぎ、鳥のさえずりなど)
副交感神経を優位にし免疫細胞の働きを助けます。
・高周波成分を含む音楽(4000Hz以上)
高い周波数が豊富な音楽は大脳を活性化し、
ストレスホルモンの低減が免疫向上につながります。
・自分が心地よいと感じる音楽
ジャンルを問わず自分自身が心地よいと感じる音楽は
強いリラックス効果と免疫力向上が見込めます。
気分とやる気の向上

音楽を聞くことで分泌されるドーパミンは
快感やモチベーションに深く関わっております。
美味しいものを食べた時や誰かに褒められた時と同じような
状態にしてくれるのです。
また明るい曲や力強いリズムの音楽は気分を高め、
落ち込んだ気持ちをポジティブに変えてくれます。
やる気がない時や集中したい時にも音楽を聴くと、
脳が活性化して集中力や作業効率が向上することがわかっています。
・アップテンポ(100〜150BPM)の音楽
脳内のドーパミンが分泌され気分の高揚とやる気向上につながります。
・クラシック音楽(特にモーツァルトやバッハなど)
高いリラックス効果が気分の改善につながります。
・応援ソングやポジティブな歌詞の音楽
前向きな歌詞によってポジティブになったり、やる気を後押ししてくれます。
・自分の好きな音楽
ジャンルを問わず自分がテンションの上がる音楽などを
聴くのがもっとも気分とやる気の向上につながります。
認知機能と思考力の向上
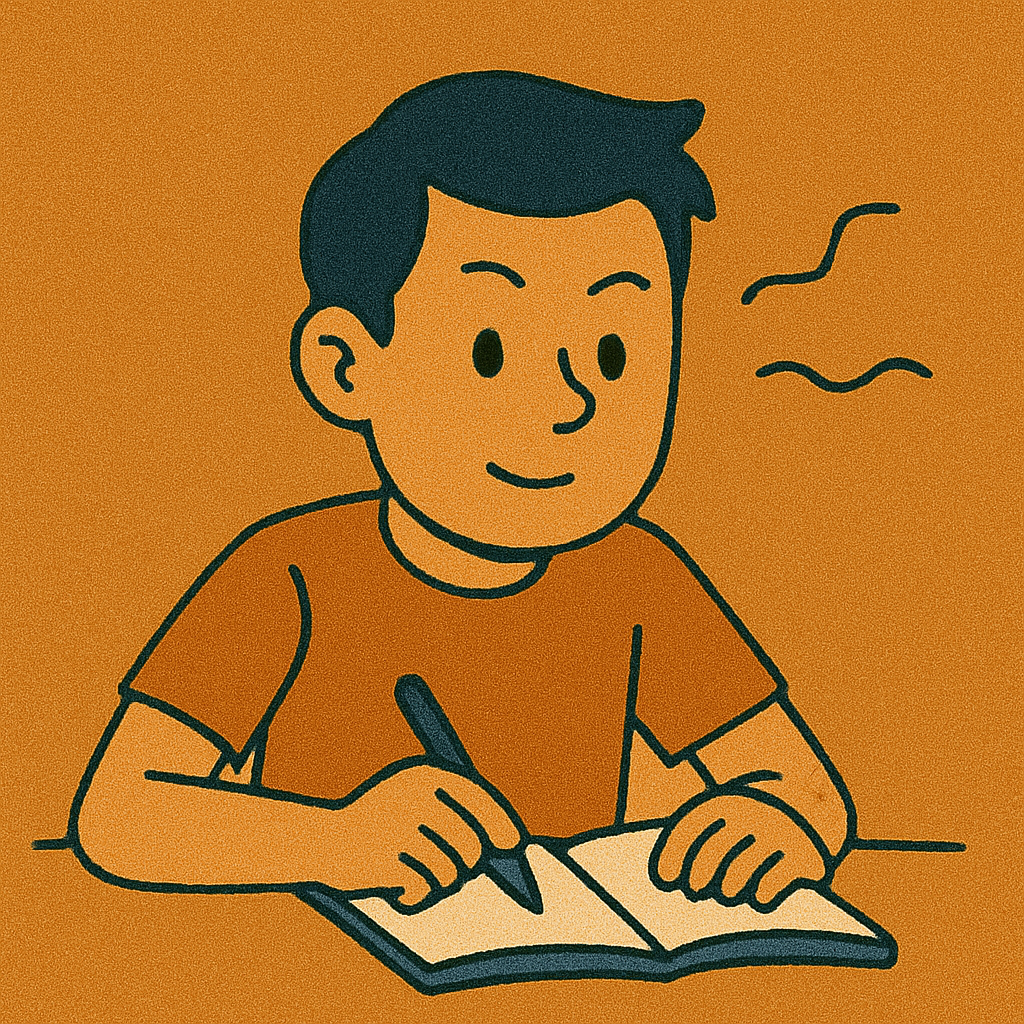
音楽は単なる娯楽にとどまらず、
脳の様々な領域を活性化させることがわかっています。
音高、リズム、ハーモニー、音色など多様な要素から成り立つため
脳内の聴覚野のみではなく前頭葉、側頭葉、後頭葉など広範な領域を
同時に刺激します。
そのことで神経回路が活性化して新たな神経結合が生まれる可能性があります。
また定期的な音楽活動が脳の灰白質の減少を抑え、
認知機能の低下を遅らせることが複数の研究で確認されています。
特にピアノのレッスンや好きな音楽を聴くことで脳の神経可塑性が促進され
記憶力や注意力が改善されると報告されています。
思考力に関しても子ども時代に音楽教育を受けたり、
楽器演奏を習慣化したりすることでIQや学力、ワーキングメモリの向上が
認められています。
・クラシック音楽(特にモーツァルトなど)
「モーツァルト効果」と呼ばれる空間認知力、思考力を高める効果が期待できます。
また論理的思考や創造性を刺激して認知機能の発達に貢献します。
・幅広い周波数や音色の音楽
右脳(感情、創造性)と左脳(論理、分析)をバランスよく刺激するために、
ピアノやフルート、チェロ、ハープなど様々な楽器で演奏された音楽は効果的です。
・自分が好きな音楽
ジャンルを問わず自分が好きな音楽は課題処理能力、ワーキングメモリが
向上することがわかっています。
痛みや疲労の緩和

音楽は聴覚を通じて脳に強い刺激を与えます。
そのことで痛みの信号を処理する脳の領域に音楽といった
別の刺激を与えることで痛みの感覚を覆い隠す効果があります。
マスク効果とも呼ばれておりこれにより痛みの強度や不快感を軽減できます。
また脳内で
β-エンドルフィン、ドーパミン、セロトニン、アセチルコリン
などの物質が分泌されることで痛みの感覚が鈍り、
精神的にもリラックスできる状態が作られます。
さらにリズムやテンポが一定の曲を聴くと
体のリズムが整い疲労回復を促進します。
・クラシック音楽(特にモーツァルトやバッハなど)
自律神経を整えて痛みや疲労の感覚を和らげます。
・自然音(川のせせらぎや鳥のさえずりなど)
リラックス効果により疲労の回復を促します。
・自分の好きな音楽
ジャンルに関係なく自分の好きな音がきが痛みの強度や
不快感を大きく軽減します。
どのように活用していくか

音楽の効果について解説してきました。
ではどのように活用していくのか。
ここまでそれぞれの効果にておすすめの音楽も紹介してきましたが、
全てにおいて効果的なものがあります。
それがクラシック音楽と自分の好きな音楽。
特に好きな音楽はどの効果も最も高く発揮されます。
クラシック音楽に関しては研究対象とされることが多いため
効果がはっきりしているためだと思いますが、
自分の好きな音楽が最も効果が高いというのは
人間の面白いところだと思います。
つまり人により効果的な音楽は違う。
でもみなさん好きな音楽の1つ2つはあるのではないでしょうか。
音楽によってより良い効果を求めるなら、
好きな音楽を聴くだけでいいというのは
なんとも拍子抜けかもしれませんね。
でも普段聴いている好きな音楽によってこの効果が
もたらされると知っていましたか?
知ることで効果は倍増される。(良くも悪くも)
プラセボ効果のようですが、
好きな音楽がさらにバフをかけてくれると思えば最高ですよね。
ぜひ自分の好きな音楽をこれからも楽しんで、
明日も頑張ってください!