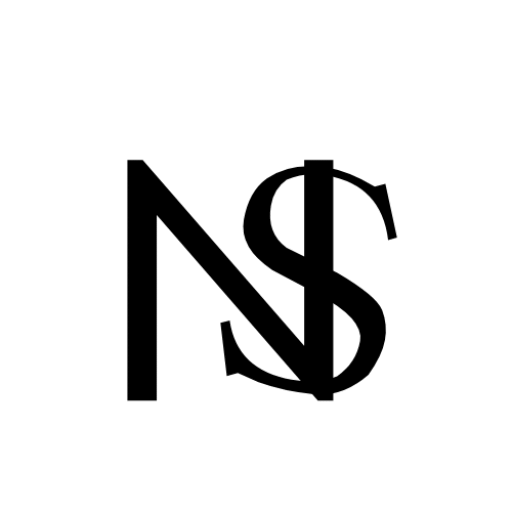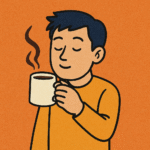現代社会に必須なストレスとの付き合い方ガイド

ストレスの無限地獄
みなさんは毎日毎日、
数多くのストレスを抱えていると思います。
あるストレスがなくなったと思ったら、
次は別のストレスが・・・
次から次へとストレスは襲いかかってきます。
それでも日々の生活のため、家族のため、
会社のため、
時には自身のプライドのために
ストレスを噛み殺して
立ち向かっているのではないでしょうか。
今回は、一見すると終わりのないようなこのストレスと
どのように付き合っていくかを徹底解説していきます。
全ビジネスパーソン、いや全人類必見です!
ストレスとは

そもそもストレスとは一体何なのか。
知っているようで意外と知らないストレスを徹底解説していきます。
まずは敵を知ることからです!
ストレスの語源
ストレスという言葉自体はもともと物理学での
「物体に外から圧がかかって歪んだ状態」を指す言葉でした。
それが現代では「外部からの刺激や圧力によって心や体に生じる緊張や負担」
を指す言葉として使われるようになりました。
また英語での「stress」の語源を辿ると、
ラテン語の「districtus(引き離す、妨げる)」や
「strictus(引き締める)」に由来してます。
この語源は「1つのものがバラバラに引き裂かれる」や
「圧力によって締め付けられる」といった意味合いを持ち、
人の心や体が外部の刺激や圧力によって不安定になる様子を
的確に表していると言えるでしょう。
ストレスの仕組み
次にストレスの仕組みについて解説していきます。
ストレスは大きく分けて3つの要素によって成り立っています。
1.ストレッサー

ストレッサーとは
ストレスの原因となる外部からの刺激や状況のことを指します。
ストレス反応を引き起こすきっかけとなります。
物理的なものから心理的なものまで幅広く存在します。
ストレッサーは主に下記の4種類に分類されます。
| 分類 | 具体例 |
| 物理的 ストレッサー | 温度(暑い、寒い)、気圧、騒音、強い光、振動、 体の痛み(外傷など)、放射線 |
| 化学的 ストレッサー | 薬品、煙、酸素の不足、食品添加物、受動喫煙、 アルコール、有機溶剤、重金属 |
| 生物的 ストレッサー | ウイルス、細菌、花粉、ダニ、カビ、寄生虫、 動物由来病原体 |
| 心理的・社会的 ストレッサー | 人間関係、家庭での役割、社会での役割、 経済的問題、人口過密、政治的問題、情報過多 |
具体例を見てもらうとわかる通り、生活を送る上で避けることはかなり難しいです。
これら4つのストレッサーがストレスの引き金となります。
2.ストレス反応

ストレッサーを引き金にストレス反応が現れます。
この時現れるストレス反応は個人差が大きく、
また同じストレッサーでも反応の現れ方が違ったりします。
ストレス反応は主に下記の3側面で現れます。
| 側面 | ストレス反応 |
| 心理面 | イライラ、不安、抑うつ、 活気の低下、集中力の低下など |
| 身体面 | 心拍数増加、血圧上昇、発汗、筋肉の緊張、 胃痛、頭痛、不眠など |
| 行動面 | 遅刻、欠勤、暴飲暴食、 飲酒や喫煙量の増加、引きこもりなど |
またストレス反応が現れる時、体の中でもさまざまな変化が発生しています。
まず、ストレッサーを受けて脳の「扁桃体」が活性化します。
「扁桃体」とは脳の辺縁系に属しており、「情動の司令塔」として
恐怖や感情処理を中心に役割を果たします。
活性化すると自律神経やコルチゾールなどのホルモンを介して、
ストレス反応を引き起こします。
この時、心拍数や血圧は上昇して体は外部の危険から備える状態になります。
でも些細なことではみなさんキレ散らかしたりしないですよね。
外に出て少し寒いくらいでガチギレする人はなかなかいないと思います。
その理由は脳の別の箇所の働きが関係しています。
「扁桃体」が活性化するとその後に「内側前頭前野」と呼ばれる
脳の前方の中央より、左右の脳半球が接する部分に位置する領域が
扁桃体の反応を抑制します。ストレス反応に対するブレーキ的な役割です。
ちなみに「内側前頭前野」では主に感情やストレスのコントロールや社会的認知、
共感、コミュニケーション、自己認知、自己制御、葛藤や意思決定など
めちゃくちゃ大事な機能を担ってくれています。
急に大きな音が鳴る→「扁桃体」が活性化(驚くなどの反応)→
「内側前頭前野」が安全だと判断し「扁桃体」を制御する→落ち着く
ただ、ストレッサーの種類や状況において
この「扁桃体」→「内側前頭前野」の順序は変動します。
予測可能なストレッサーの場合は事前に「内側前頭前野」が活性化して
先に「扁桃体」の活性化を制御することが分かっています。
確かに同じ度合いの不都合でも、
想定していた方が気持ち的に楽ですよね。
実際に体の反応がそうなっているのです。
大きな音が鳴ると知っている→「内側前頭前野」が事前に「扁桃体」を抑制
→大きな音が鳴る→「扁桃体」は過剰に反応することなく冷静でいられる
このようなストレス反応ですが、生物として重要な役割を果たしています。
それは些細な外部刺激でもすぐに反応して、
立ち向かったり、逃げたりをできるようにしてくれています。
これによって他の動物や敵から自身の命を守ってきたのです。
また慢性的にストレッサーを受けたり、強いストレッサーを受け続けると
「扁桃体」の神経回路に構造的な変化が起こり、制御が効きづらくなります。
さらにこの状態だと些細なストレッサーでも「扁桃体」が反応しやすく
なってしまいます。
3.ストレス耐性

ストレス反応に対してどのような対応をしていくかは個人差がかなり大きいです。
同じ状況でもブチギレてしまう人、冷静でいられる人、我慢できる人、
そもそも何も感じない人など10人いれば10通りの反応があると思います。
「扁桃体」「内側前頭前野」の働きの違いもありますが、個人の過去の経験や
思考、能力も関係してきます。
それらストレス反応に対する耐性を6つの要素
で解説していきます。
①容量
ストレス反応をどれだけ受け止めれて、溜められるかという許容範囲のこと。
容量が大きい人は多少のストレス反応でも心身の不調を感じにくい。
容量には個人差が大きく、心身の状態や経験によっても変動する。
②感知能力
ストレッサーを感知する能力のこと。
「内側前頭前野」によって「扁桃体」を先に制御することが多くなる。
また、感知能力が低い人はストレッサーを感じにくい反面
気づかないうちに蓄積してしまうリスクもある。
③処理能力
ストレス反応の原因に対処、問題を解決したりする能力のこと。
問題解決力や柔軟な対応力が高いほどストレス耐性は高くなる。
④経験値
過去に似たストレッサーからストレス反応を受けているという経験の有無など。
経験値が多い人ほど適応能力が高まる。
何度も同じストレッサーに直面するとことで耐性が強化される。
(慢性的、強いストレッサーの場合は「扁桃体過敏」になる可能性あり)
⑤回避能力
ストレッサーから物理的、心理的に距離をとる能力。
ストレッサーを受け流したり、割り切ったり、断わったり、
その場から離れることができるようになると耐性が強化される。
⑥転換能力
ネガティブな状況でもポジティブに捉えなおしたり、
失敗を学びとして前向きに受け止める能力のこと。
気分転換やリフレッシュすることもこの能力に含まれる。
この6つの能力がストレス耐性となります。
これらの耐性は生まれつきの気質や性格だけでなく、育った環境や過去の経験、
現在の状況や健康状態、生活習慣などの多くの要因で決まります。
なので人によって千差万別の反応があるのです。
ストレスとどのように付き合っていくか

ではそんなストレスとどのようにして付き合っていくべきなのか。
前提としてストレスは命を守るための機能である。
他の動物や敵から身を守るためのものである。
でもみなさんはそんな経験を日常的にします?
野生動物に急に襲われたり、
武器を持った人に襲われたりなど
命の危険に晒されることは現代社会において、
ましては日本おいては滅多にないと思います。
それでも日常的にストレスを感じているのは事実ですよね。
そうです。
実際には命の危険はないとわかっていても体はその区別ができず、
常に危険だと判断し続けているのです。
私たちの体は命を守ろうと必死になって役目を果たしてくれています。
そう思うとストレスも少し微笑ましく思えますよね。
(ストレス感じている時は微塵も思いませんが)
ではどのように付き合っていくか。
それは自身のストレス耐性を強化する。
そしてストレスを弱める。
このことが現代のストレス社会を生き抜くビジネスパーソンの必須スキルです。
でも何をしたらいいかわからないよ!という人向けに
超具体的に全能力を上げる方法をご紹介いたします。
客観的に認識する
まずは自分がどの時にストレスを感じていてるのかを客観的に把握しましょう。
思い返してみていつ、どんな状況で、自分のその時の感情は、場所は、
誰といたかなど限りなく詳細に紙などに書き出します。
そしてそのどの箇所がその時のストレスの原因だったかを見つけ出します。
普段頭の中で考えてもモヤモヤするだけの人は多いと思います。
私も頭の中だけで延々とモヤモヤしまくっているタイプの人でした。
しかし紙に書き出すことで自身の頭の中でモヤモヤ考えていることを
外に出すことができ客観的に考えることで案外あっさりと原因を
見つけ出すことができたりします。
人間、意外と自分のことをわかっていなかったりします。
他人には的確なアドバイスや冷静な意見を言えても自分にはなかなかできないのは
この客観的な視点がないからです。
まずは自身のストレスを客観的に見つめ直してみてください。
対応や対策を考える
客観的に見つめ直した後は原因に対して対応や対策を考えていきます。
この時に参考にしてほしいのは6つのストレス耐性の視点です。
そのストレスへの容量はどうなのか、感知能力は使えるのか、
問題解決はできるのか、経験が必要なのか(慣れ)、
逃げたり離れたりすることはできないか、
このストレスから何を学んで、生かせるのか。
これらの視点で考えると対応や対策が出てきやすいです。
私もこの6つの視点から、
自身のストレスに対して客観的に考えることを
始めてから同じようなストレスに悩むことが減りました。
同時に新しいストレスが学びのチャンスと思えるようになりました。
ストレスを感じている時は気分は良くないですが、
帰ってからノートで客観的に分析していき自身の成長の糧にしています。
もちろんだいぶ理不尽な状況もあります。
それでも必ず学んだことや自身に足りなかったことが見えてきます。
(それでも明らかに理不尽な嫌がらせや暴言、
暴力などは一人で抱えず、しかるべき相手に相談した方が良いです。
事前にそのラインを決めておくのも一つの対策です。)
次、ストレスを感じたら
「よし!レベルアップきた!」って思ってみてもいいかもしれません。
生活習慣を整える
やはり人間の基本は「睡眠・食事・運動」となります。
十分な睡眠時間を確保して質の良い睡眠をとり、
バランスの良い栄養のある食事をして、
適度な運動をする。
ストレスと付き合う上でも生活習慣は土台となります。
ここがしっかりできていないとストレスともうまく付き合えません。
ストレスを抱えていると自暴自棄になってしまいがちです。
自分の存在がどうでも良くなってしまう。
睡眠を取らなくなったり、
明らかに体に良くないものをひたすら暴飲暴食したり、
全く運動もせず部屋にこもったりしてしまう。
私も経験があります。
しかしその時にうまくいったことなんてほとんどありません。
自暴自棄になっている間もどんどん自己嫌悪していきます。
うまくいかない日もあります。
時にはヤケ酒したり、ファストフードをドカ食いしたり、
深夜まで映画を見たり、ゲームしたり、
自分の欲を発散するのも良いでしょう。
それでも次の日には何もなかったかのように生活習慣を整える。
大丈夫です。また生活習慣を戻せます。
絶対大丈夫です!
まとめ

今回はストレスとの付き合い方について徹底解説をしてきました。
ストレスとは、
ストレッサーをきっかけにして
ストレス反応が現れる。
しかし、ストレス耐性の有無で人によって現れ方が千差万別である。
そしてストレスは本来、体が命の危険に備えるためのものである。
そんなストレスとの付き合い方は、
まず自分のストレスを客観的に認識して
ストレス耐性6つの視点から対応や対策を考える。
そして基本である生活習慣を整えておく。
何度も繰り返しになりますが、
現代社会においてストレスは毎日のように襲いかかってきます。
それでも希望はあります。
なんせストレスは体が危険を感じているサインだから、
自身がまだ対応できていないよ、準備不足だよ、
この場所は自分に合っていないよ、逃げた方がいいよなど
気づいていないことを教えてくれているのです。
それならその声を聞いてあげてみてください。
聞き方は客観的に。
主観ではなかなか聞き取りづらいですから。
事実、自身の出している声と他人が聞いている声は違います。
自分の外に出してみて初めて気づくことも多いはずです。
長い人生、まだまだたくさんのストレスと出会っていくと思いますが、
みなさんなら乗り越えられると心から思っています。